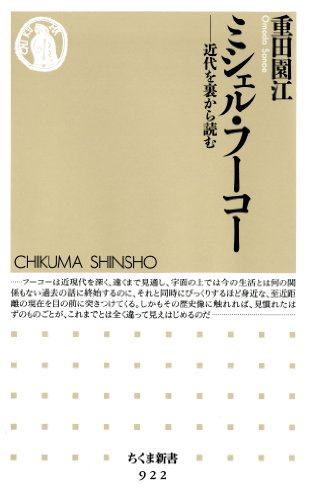1.反共感論――社会はいかに判断を誤るか(ポール・ブルーム)
心理学者による道徳的共感の批判とでも称せるでしょうか。「共感」を元手にすると、「共感できないから擁護しなくていい」という結論に安易に至ってしまうので、問題は「共感できない相手」をいかに理解するかという話なのかなと。前回の10冊のうち最後に入っていたトム・ニコルズの『専門知は、もういらないのか』とある種かぶる部分のある本でした。良いと思います。現代の、SNSで共感をベースに繋がることのメリットとデメリットについてもつまびらかにしていたと思います。
道徳論みたいな話もちらほら出てくるんですが、これに関しては若干の哲学に関する知識がないと批判的には読めないかもしれません。そこへの言及は微々たるものですが。
2.いのちの初夜(北条民雄)
Kindleを最近読むようになりました...。倫理関連の書籍・文献を渉猟しているときに、いくつかハンセン病患者のインタビューに触れて、この著者について思い出しましたので、自分にとっての記念すべき一作目となりました。
著者はハンセン病の当事者で、この作品は診断がおりてから入院した当初の生活について書かれたものです。小説を読むのが随分久しぶりなので、なんとコメントしてよいものか若干悩みますが、よい作品であったと思います。今までの日常からゆっくりと隔絶され、患者たちの日常について考え、見聞きするさまが克明に描かれています。
3.通信の数学的理論(クロード・シャノン, ワレン・ウィーバー)
誰に勧められるともなくなにかで発見して読んだんですが(n番目の心の積読だった)、これを借りてる間にシャノン限界の話が出てきてなんとなく運命を感じました...(?)
メッセージの送受信に関する数学的背景とそれに対する工学的(物理的?)限界なんだけど情報理論の時点で既にわからない上に電力がどうこういいだして無理ゲーでした。もちろん元より読めるとは思っていないんですが。確率に対する情報のエントロピーとか、符号化したメッセージの冗長性とか意味論的なところについては面白いなと思って読みました...自然言語の情報量とか。あとは、通信のもつ3段階の最終において「意味の解釈」があって、いや当たり前なんですが、コミュニケーションの理論ではよく出てくる内容が軽く触れられていることについては哲学の人が読んでも面白いのではなかろうかと思います。
半分自分のメモ
I 離散的無雑音システム
確率過程)
ある確率に支配されて記号の系列を生み出す物理的システムないし数学的モデル。
自然言語の場合にも確率過程を適用することができ、その場合は離散的な方法をとる。自然言語の場合はメッセージの冗長性が高く、通信の後に意味の生成を行う必要がある(通信→意味→効果)
コミュニケーションの哲学っぽくて若干面白い(数式はまったくわからない、確率が曖昧であればあるほどエントロピーが大きくなるということくらい)
4.方法への挑戦―科学的創造と知のアナーキズム(P.K.ファイヤアーベント)
1
このことは歴史的エピソードの探究によっても、また観念と行動との間の関係の抽象的分析によっても示される。進歩を妨げない唯一の原理は、anything goes(なんでもかまわない)である。
2
たとえばわれわれは、よく確証された理論、および/あるいは、よく確立された実験結果と矛盾する仮説を用いることができる。われわれは科学を反帰納的に推し進めることによって進捗せしめることができる。
3
新しい仮説は受容されている〈理論〉に一致しなければならない、という整合性の条件は、旧い理論を保存するものであって、より良い理論を保存するものではないのだから、非理性的である。よく確立された理論と矛盾する仮説は、他のどんな方法によっても得られない証拠をわれわれに提供する。理論の増殖は科学のために有益であるが、斉一性は科学の批判的能力を損うことになる。斉一性はまた個人の自由な発展をも危うくする。
4
いかに古くばかげたものであっても、われわれの知識を改良する能力をもたない観念は存在しない。思想史の全体が科学に吸収され、理論の一つ一つを改良するのに用いられる。政治的な干渉も拒否されない。現状(status quo)に対抗するものに抵抗する科学の熱狂的排外主義を克服するために、政治的干渉が必要とされることもあり得る。ーP.K.ファイヤアーベント『方法への挑戦』
5
どんな理論も決して、その領域内のすべての〈事実〉とは合致しないが、しかも常に理論の方が悪いわけではない。事実はより旧いイデオロギーによって構成されており、事実と理論との衝突は進歩の証明でありうる。それはまた、身近な観察上の概念に潜むいろいろな原理を見出そうとする試みの最初の一歩でもある。8
変換によってひき起こされる当初の困難は〈アド・ホックな仮説〉によって切り抜けられるが、アド・ホックな仮説はこのように時に積極的な機能を有する。それは新しい理論に息をつく暇を与え、未来の研究の方向を指示する。9
自然的解釈に加えて、ガリレイはまた、コペルニクスにとって危険と思われる〈感覚〉をも変化させる。ガリレイは、そのような感覚が存在することを認め、コペルニクスがそれを無視したということで彼を賞讃し、〈望遠鏡〉の助けでそれを取り除いたと主張する。しかし彼は望遠鏡が一体なぜ天空の真実の姿を与えると期待されるのか、その〈理論的〉な理由は少しも与えない。
それぞれの章に短いまとめがついているんですが、半ばの実例に対する批判に関してはまとめだけ読んでもいいのかもしれません。
今現在に至ってももっとも強力な部分は、恐らくポパーの反証可能性に対して反駁したこと。そもそも科学において発見された事実に対して、反証するプロセスそのものが方法論的にイデオロギーを踏襲しているに過ぎないと。そこから新しいものは生まれないんじゃないか?という問いが、常に方法論に対するアナーキズムを含んでいると。面白いけどパンチきいてますね。
絶版になってるけど絶版にするには惜しいと思います、カール・ポパーの『科学的発見の論理』もそうだけど…(売れないから刷り直してくれないのはよくわかる)
5.カール・マルクス: 「資本主義」と闘った社会思想家(佐々木隆治)
マルクスの『資本論』、全13巻くらいのうち1巻しか読んだことがないままにきてしまったので何か軽く読めるものがないかな...と探してこれにいきあたりました。ちくま新書のセールはめちゃ秀逸です(宣伝)。あとは『まんがで読破』シリーズの資本論を読んだくらいか。
晩年のマルクスが農耕や生化学まで手を伸ばしていたのは全然知りませんでした。共産主義に汚された(?)マルクス論を読みたくなかったんでこれわりとよかったです。
6.ミシェル・フーコー: 近代を裏から読む(重田園江)
規律の体系において高く評価される者とは、他より抜きん出た者や類を見ない才能を持つ者ではなく、規格に合わせる能力と判断力を持ち、集団そのものが設定する基準=規格に適合する行為や発言ができる者だ。
権力は人の相互行為を通じて、戦略的に作用する。そして日々新たに犯罪者とそうでない人の境界線を引きなおし、被害者意識を醸成し、安全への際限ない欲望を煽る。家族のため、わが子のために安全で安心な街が必要だ。犯罪者集団を刑務所に送り、「頭のおかしいやつら」を病院に入れることは大切だ。彼らは私たちとは違う「危険人物」なのだから。
若干著者のクセが強かったけど『監獄の誕生』を読む機運が高まったのは良かったと思います。本自体をお勧めできるかといわれると....微妙....放送大の教科書(『現代フランス哲学に学ぶ』)とかのほうがよほどよく説明していると感じます...
7.社会学的想像力(C.ライト・ミルズ)
人間とは隔絶されたような客観的な変化から身近な自己の親密性へと眼を移し、そして両者の関わりを見ることのできる能力である。それが駆動している背後には、個人がひとりの特徴ある存在として生きている社会・時代において、自分が社会的・歴史的にどのような意味をもっているのかを知ろうとする衝動が必ずある。
つまり、だからこそ人々は手段としての社会学的想像力を用いて、一方で世界において起こっていることを把握し、他方で社会における個人史と歴史とが交差するささやかな地点としての彼ら自身において何が生じているのかを理解したい、と望むのである。
経験調査の方法について開発者のひとりと話すときには、いつも、相手は知性の持ち主だと感じる。しかし、若者が三、四年もこうした類いの調査方法を学んでしまったような場合は、現代社会研究という問題について彼と話すことはまずもって不可能なことになる。彼の地位も、キャリアも、野心も、そしてなにより自尊心も、この一つのパースペクティブ、一つの語彙、一組の技法に大部分が基づく。実は、彼はそれ以外のことを何も知らないのである。
哲学的研究は実際の社会科学の研究において役立つものである、と私も思う。哲学的研究を知ることで、自分の概念や研究手順を、よりはっきり意識し、明晰にしてゆけるだろう。こうした作業のための言葉を、哲学的研究は与えてくれるだろう。しかし、哲学的な議論の効用はあくまで一般的な性格のもので、社会科学の研究現場で哲学モデルを真に受ける必要はない。なによりも私たちは、モデルで問題を限定したりせず、想像力を解放して、研究のヒントを得るようにしなければならない。「自然科学」をふりかざして、研究する問題を狭隘に限定するのは臆病であるように思われる。もちろん、未熟な調査者が問題の限定を望むような場合は、賢い自制になりうるかもしれない。しかし、度が過ぎる限定には、なんら意味のある根拠はないのである。
人間の多様性には、個々の人間の多様性も含まれる。社会学的想像力は、それも把握し理解しなければならない。この想像力のなかでは、一八五〇年のインドのバラモンが、イリノイの開拓農民と並んで立っている。一八世紀の英国ジェントルマン、オーストラリアのアボリジニ、一〇〇年前の中国人農民、今日のボリビアの政治家、中世フランスの騎士、一九一四年のハンガーストライキ中のイギリスの婦人参政権論者、ハリウッドスターの卵、古代ローマの貴族が、並んで立っている。「人間」について書くということは、これらのすべての男性と女性について──ゲーテについても隣の家の少女についても──書くということである。 社会科学者は、人間の多様性を秩序だてて理解しようとする。しかしこの多様性の幅と深さを考えると、こう尋ねられるのも無理もない。それは本当に可能なのか? 社会科学の混乱は、現場の社会科学者が研究しようとしている対象を反映しているのだから避けがたいのではないか? 私の答えはこうである。その多様性はおそらく、そのごく一部の単なるリストがそう見えるほどには「無秩序」ではない。さらに、大学で提供される履修コースがそう見えるよりも、無秩序ではないかもしれない。秩序も無秩序も、観点次第である。人間と社会の秩序だった理解に至るためには、理解を可能にするほどシンプルでありつつ、人間の多様性の幅と深さを視野に収めることのできるほど包括的な、一連の観点が必要である。そのような観点を求める苦闘は、社会科学の最も重要で永続的な苦闘なのである。
単に経済学的な「価格理論」は、論理的には整っているかもしれないが、経験的に適切なものではありえない。そのような理論には、たとえばビジネス組織の経営陣と組織内外の意思決定者の役割についての考察が必要であるし、費用特に賃金についての予期の心理学への注意が求められる。小事業カルテルによる価格操作に対しては、その先導者たちを理解せねばならない。同じように、「利子率」を理解するためには、非個人的な経済の仕組みだけでなく、銀行家と政府役人の間の公私の往来についての知識がしばしば必要である。 私の考えでは、それぞれの社会科学者が社会科学に参加して、その際十分に比較を行う以外にできることはない。そしてそれは、今では完全に力強い重要な傾向であると私は信じている。比較研究は、理論的なものも経験的なものも、今日の社会科学の発展にとって最も将来有望な方向性である。そしてそのような研究は、統一された社会科学のなかで最もうまく行うことができる。
学問の知の内容について言えば、今日の中心的な事実は境界線がますます流動的になっていることである。概念はますます容易に、学問分野間で汎用される。一つの分野の語彙をマスターして、それを別の伝統的領域で巧妙に使うことだけでキャリア形成をしているような著名な人が何人かいる。専門化は存在するし、これからも存在するだろうが、それは、私たちが知っているような多かれ少なかれ偶然できあがった学問分野による専門化であるべきではない。それは問題に基づいて専門化されるべきであり、その問題の解決には、複数の学問分野に伝統的に属する知的能力が必要なのである。すべての社会科学者によってますます類似の概念と方法が使われるようになる。
ある個人の生活は、その個人史が生きられる制度との関係なしに適切に理解することはできない。というのもこの個人史は、獲得、落伍、軌道修正、そして最も個人的な意味では一つの役割から別の役割への移動の記録だからである。人はある特定の種類の家族の子どもであり、ある特定の種類の子ども集団の遊び仲間であり、学生、工員、職長、将軍、母親である。人生の大半は、特定の制度内部でそのような役割を演じることから成っている。ある人の個人史を理解するためには、その人がどんな役割を演じてきて、今なにを演じているか、それはどんな重要な意味をもっているかを理解しなければならないし、その役割を理解するためには、それが組み込まれている制度を理解しなければならない。
もし人々が関心をもつことだけが私たちにとって重要だという素朴な民主的見解をとるならば、既得権益によってしばしば偶然に、そしてしばしば意図的に教え込まれた価値を私たちは受け入れていることになる。これらの価値は、人々が展開させる可能性のあった唯一の価値であることがしばしばである。それは、選択というよりも、無意識的に獲得された習慣である。 もし人々が関心を持とうが持つまいが、人々のためになることだけが私たちにとって正しく重要なことである、というドグマティックな見解をとるならば、私たちは民主的価値を侵害する危険を冒すことになる。私たちは、人々が一緒に理性的に考えようとする社会、理性の価値が高く評価されている社会における説得者というよりも、操縦者か強制者か、またはその両方になるかもしれない。 私が提案しているのは、公的問題と私的問題に取り組み、それらを社会科学の問題として定式化することである。それによって、自由な社会における人間の事象にとって、理性が民主主義的な意味で有意義なものになり、私たちの研究の約束の根底にある古典的価値が実現される可能性が最も高くなるのである。私はそれしかないと思う。
引用が多くなってしまいました。画一的・斉一的な方法論を繰り広げる社会学の方法論の硬直性を批判し、諸科学を集合することの意義を説いています。ファイヤアーベント『方法への挑戦』の内容と少しかぶるところがありますが、こちらは人文諸学に対するものという感じです(向こうは科学の方法論批判なので)。
8.たたかう植物: 仁義なき生存戦略(稲垣栄洋)
淡々と説明だけが進むし些か情緒趣味が過ぎるのと、植物以外の面(環境問題とか)については素人さんやなという印象が拭えなかったけど肝心の植物の特性については面白かったのではないかと思います。
植物が外敵から身を守る方法、外敵や環境の種類に合わせた生存戦略については細かく書かれているかなと。妙に属人的というか人間的属性を付与しているのはあんまり好きではなかったです。新書なので仕方ない。
9.人間の学としての倫理学(和辻哲郎)
かく見れば人倫五常の思想は、人間共同態を父子・君臣・夫婦・昆弟・朋友というごとき五種の類型において把捉する立場に立ち、これらの共同態をその存在根底から眺めたものである。
…人は社会学を独立させた時に、社会もまた人間存在の一つの仕方であることを閑却して、それを「人の学」に対立せしめたのである。このことは「人」の把捉を誤らしめるとともにまた「社会」の把捉を誤らしめる。十八世紀の個人主義が孤立せる「人」から社会を説いたのは誤りであったとしても、それを脱するために社会を人から離すこともまた正しくない。社会は「人間」である。社会の学は人間の学でなくてはならない。従ってそこでの根本問題は人と人との間柄である。個であるところの「人」がいかにしてまた同時に「共同態」であるか、総じていかなる行為の仕方が人間の団体というごときものを可能にしているのであるか、それがここで根本的に解かれねばならない。かく見れば社会の学は本来倫理学と異なるものではないはずなのである。
本当は全集の9巻を借りたのですが、他のところを読む前に返却してしまったのでこの部分だけを文庫化した本を載せております...
日本の哲学の古典にして、倫理学をAnthropologie(人間についての学)として基礎づけています。カントの『実践理性批判』からヘーゲル『精神現象学』の註釈を経て自己意識の内在性を「もの」ではなく「こと」として、つまり人間同士の交わり(共同態)と定義することで倫理学を「社会についての現象を記述する学」と言い換えます。
日本の近代哲学読んだことなかったので面白かったですがめちゃくちゃ難しい...
10.アルツハイマー病の謎—認知症と老化の絡まり合い—(マーガレット・ロック)
面白かったです、面白かったですがそこそこ難しかったです。医療の素人だとついていくのはそこそこ厳しいと思われます、というか自分もついていけない箇所がいくつもありました。遺伝子変異とか、あるとは聞くけど詳細については全然知らん、みたいな。
認知症全般に広くかかわる機会がありそうなので適当に検索して面白そうなものを借りてきたのですが、そういう意味では予想以上でした。
特にまだはっきりとした疾患のメカニズムも確定しておらず、定義が曖昧で論争のある疾患(症候群と呼ぶべきかもしれないと本書の中では言われていますが)です。治験や検査をすることの負担・意義について繰り返し述べており、それが認知症患者(またはMCIと呼ばれる前駆状態——これにも論争があります)自身のQOLにとって良いものといえそうかどうかなど、疫学的問題点以外にも社会問題としてとらえることができます。あと大規模コホートのやりにくさについても、なるほど確かにしっかり定義されていないものについて追跡するのは難しいんだなあと思いました。
それから、たびたび科学哲学の方法論と分析系の心の哲学にふれ、特に後者についてはアルヴァ・ノエのエナクティブアプローチを借用していました。個人的にセンスがいいなと感じたポイントです。疾患の定義やとらえ方について、科学の方法論が手探りであるとき、暫定の解(または個人が解釈するために有用な情報)としていまの哲学は十分に対応しうると思います。
ちょっとずつ認知症全般について学んでいく予定です。この本だけは読み物ジャンルだったのでここに挙げました。